脳神経外科について
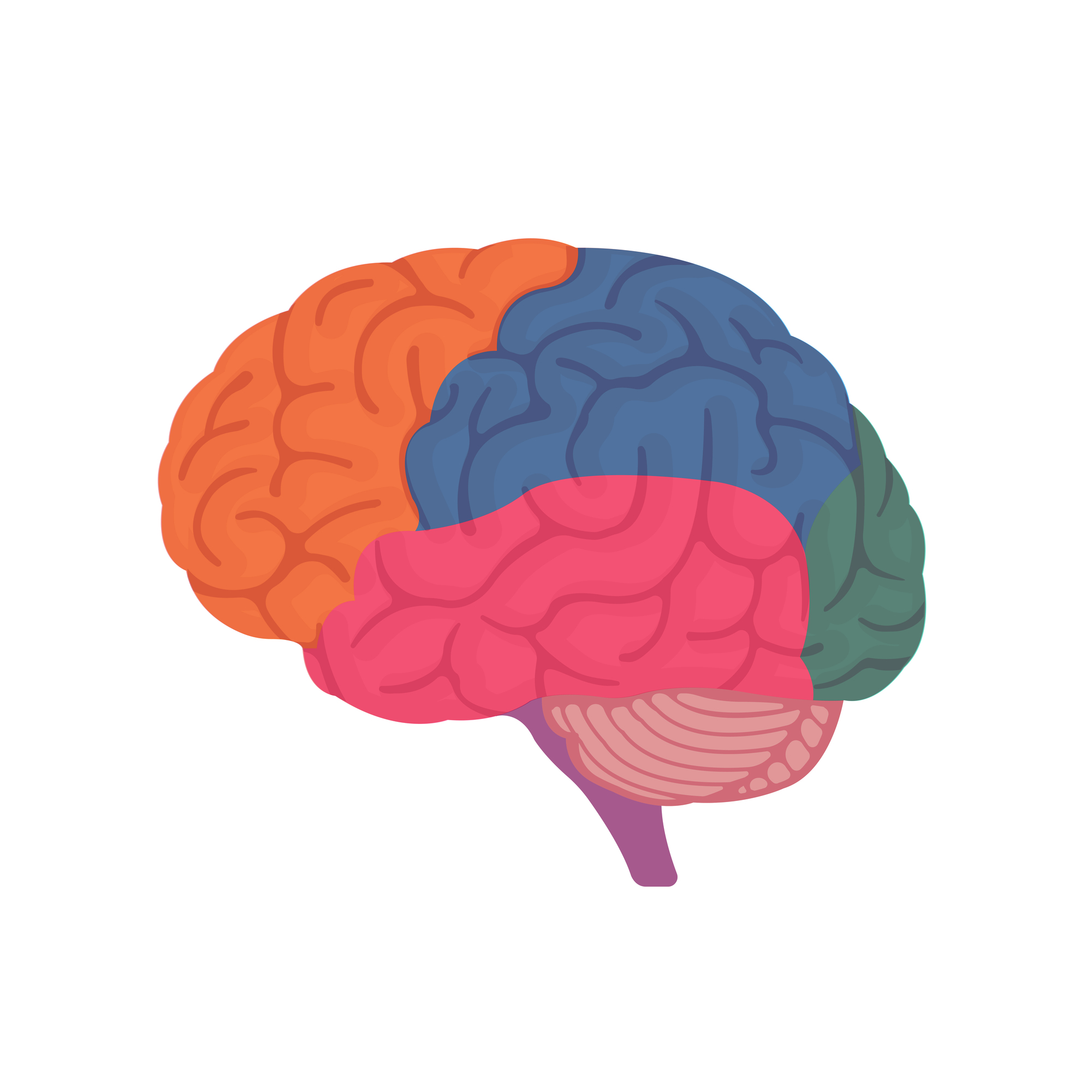 脳神経外科は、脳や脊髄、末梢神経、骨・筋肉・血管などの付属機関を含む神経系の異常・疾患を専門とした診療科です。
脳神経外科は、脳や脊髄、末梢神経、骨・筋肉・血管などの付属機関を含む神経系の異常・疾患を専門とした診療科です。
対象となる主な疾患には、脳内出血・くも膜下出血・脳梗塞などの脳卒中、脳動脈瘤などの血管障害、水頭症、慢性硬膜下血腫、脳腫瘍、頭部外傷などが挙げられます。受診される患者様は、頭痛や痺れ、ふらつき、脱力、めまい、耳鳴りなど症状を訴えることが多く、これら症状は脳疾患の症状として起きていることも考えられます。
当院では、MRIやCTなどの高度な検査を行える最新鋭の医療機器を採用しており、疾患の早期発見・早期治療に注力しています。お悩みの症状がある方は、一度当院までご相談ください。
MRI検査
MRI検査とは
 MRI検査とは、強力な磁石と電磁波を利用し、全身、脳や脊髄など、身体の内部の断面画像を撮影する検査です。放射線を照射することはないため、被ばくの恐れもありません。
MRI検査とは、強力な磁石と電磁波を利用し、全身、脳や脊髄など、身体の内部の断面画像を撮影する検査です。放射線を照射することはないため、被ばくの恐れもありません。
-
脳の検査:
脳とその周りの断面図を画像化し、脳腫瘍や脳梗塞、水頭症などの疾患や脳萎縮の有無などを調べます。 -
脳血管の検査(MRA):
血管狭窄、血管奇形、動脈瘤の有無を調べます。 -
脊椎・脊髄の検査:
脊髄の働きを妨げる、神経の圧迫、血流の低下、腫瘍などの有無を調べます。 -
その他:
当院では他院からの紹介にも対応しており、腹部のMRCP、膝、肩など全身の検査を行えます。
検査をお勧めする方
- 頭痛や痺れ、めまい、物忘れなど脳に関する症状が出ている方
- 脳卒中の不安がある方、脳卒中の既往歴がある方
以下の疾患の可能性がある方は検査を受けましょう
- 脳血管疾患(脳動脈瘤、動静脈奇形、内頚動脈狭窄症、もやもや病)
- 脊椎・脊髄の疾患
- 脳の外傷による軽度の損傷
- 脳の先天奇形
- 脳腫瘍
- てんかん
- 認知症の鑑別診断
- 体の震え・痺れ
- 意識消失
MRI検査の流れ
1MRI検査用の問診票に必要事項をご記入ください。
2担当より検査について説明を行います。
3説明後、検査着に着替えて頂きます。
4検査を開始します。
横になってできるだけ静止した状態を保ってください。個人差がありますが、検査の所要時間は40~50分ほどとなります。
5私服に着替えて頂き、検査結果が出るまでお待ち頂きます。
※アクセサリーやカラーコンタクトは検査前に外して頂きます。
※検査中に大きな音が鳴りますが、機械なのでご安心ください。
※検査中に気分が悪くなった場合、すぐに連絡ブザーを押してください。
CT検査
CT検査とは
 CT検査は、少量の放射線を使用し、脳や血管の状態を調べる検査です。
CT検査は、少量の放射線を使用し、脳や血管の状態を調べる検査です。
MRI検査に比べて検査時間が短いことがメリットの1つです。CT検査で脳を調べる場合、外傷による骨折や出血、脳卒中などがあれば、その部分が白く表示されます。
また、立体的な画像を得られるため、骨折なども詳しく把握することが可能です。さらに、胸腹部や肺の疾患、四肢の骨折なども発見するのにも有用です。
CT検査をお勧めする方
- 脳出血や頭蓋内出血が疑われる方
- 頭部の損傷による頭蓋骨の骨折の有無を調べたい方
- 頭蓋骨の疾患の有無を調べたい方
- 水頭症の有無を調べたい方
- 上記以外の脳の疾患の有無を調べたい肩
CT検査は比較的検査の時間が短く、基本的に年齢制限はありません。
また、体内に金属がある方、閉所恐怖症の方など、MRI検査を受けられない場合もCT検査は問題なく受けられます。
CT検査の流れ
検査室での滞在時間は5分ほどで、検査自体は20秒~1分ほどで終ります。
1頭部CTでは検査着に着替えて頂く必要がありません。頭部以外の部分は、服に付属する金属が検査の障害となるため検査着に着替えて頂くことが必要です。
2検査を開始します。横になってできるだけ静止した状態を保ってください。
3検査中、医師より指示を出します。
4検査が終わりましたら、担当より結果を説明させて頂きます。
脳神経外科の主な症状
めまい
 めまいの発生原因は、脳の異常、耳の異常、循環障害や内科的要因の3つに大別されます。
めまいの発生原因は、脳の異常、耳の異常、循環障害や内科的要因の3つに大別されます。
また、めまいと聞くと目が回るイメージを持たれている方が多いですが、身体が宙に浮いている感覚、ふらつく感覚、頭がぼーっとする感覚などもあります。目が回る回転性のめまいは、原因に応じて伴う症状は異なり、また、症状の感じ方や出方は人によって異なります。自己判断は控え、めまいが起きた場合はすぐに当院までご相談ください。
脳の異常が原因となる場合、脳出血や脳梗塞などの深刻な疾患の初期症状として起きている恐れがあります。そのため、脳が原因のめまいは特に早期治療が大切です。
頭痛
 頭痛は2種類に大別され、疾患などの原因なく発生する「一次性頭痛」、脳疾患などが原因となる「二次性頭痛」があります。
頭痛は2種類に大別され、疾患などの原因なく発生する「一次性頭痛」、脳疾患などが原因となる「二次性頭痛」があります。
一次性頭痛は、お薬の服用により症状を改善でき、危険性は比較的高くありません。一方、二次性頭痛は、脳出血やくも膜下出血、髄膜炎、脳腫瘍、慢性硬膜下血腫などが原因となり、なるべく早めに専門医による治療を受ける必要があります。
頭痛はありふれた症状ですが、なかには二次性頭痛のように深刻な疾患が原因となる頭痛もあるため、自己判断は控えましょう。当院では、まずは問診にて頭痛が発生したタイミング、持続時間、頻度、痛みの感じ方などを丁寧にお聞きし、必要に応じてMRI検査やCT検査を行い、頭痛の種類に応じた適切な治療を提供しています。
痺れ
 痺れと一言で言っても、その感じ方は様々です。
痺れと一言で言っても、その感じ方は様々です。
例えば、「ジンジンする」「電気が走るような感覚」「手足を動かしづらい」「触っても感覚がない」などの感じ方があります。また、原因も様々ですが、脳や脊髄の疾患が原因となっていることもあるため、原因の特定が必要です。当院では、痺れの原因を特定し、それに応じた適切な治療を提供しています。
担当医師表
| 受付時間 | 土 |
|---|---|
| 午前 8:00~11:30 | <第1・3・5> 大岡 史治 <第2・4> 芝 良樹 |
※諸事情により担当医師が変更したり、休診させていただく場合がありますので、休診情報をご確認ください。
※急な変更の場合は休診情報の更新が間に合わない場合があります。申し訳ありませんが、お電話での確認をお願い致します。









